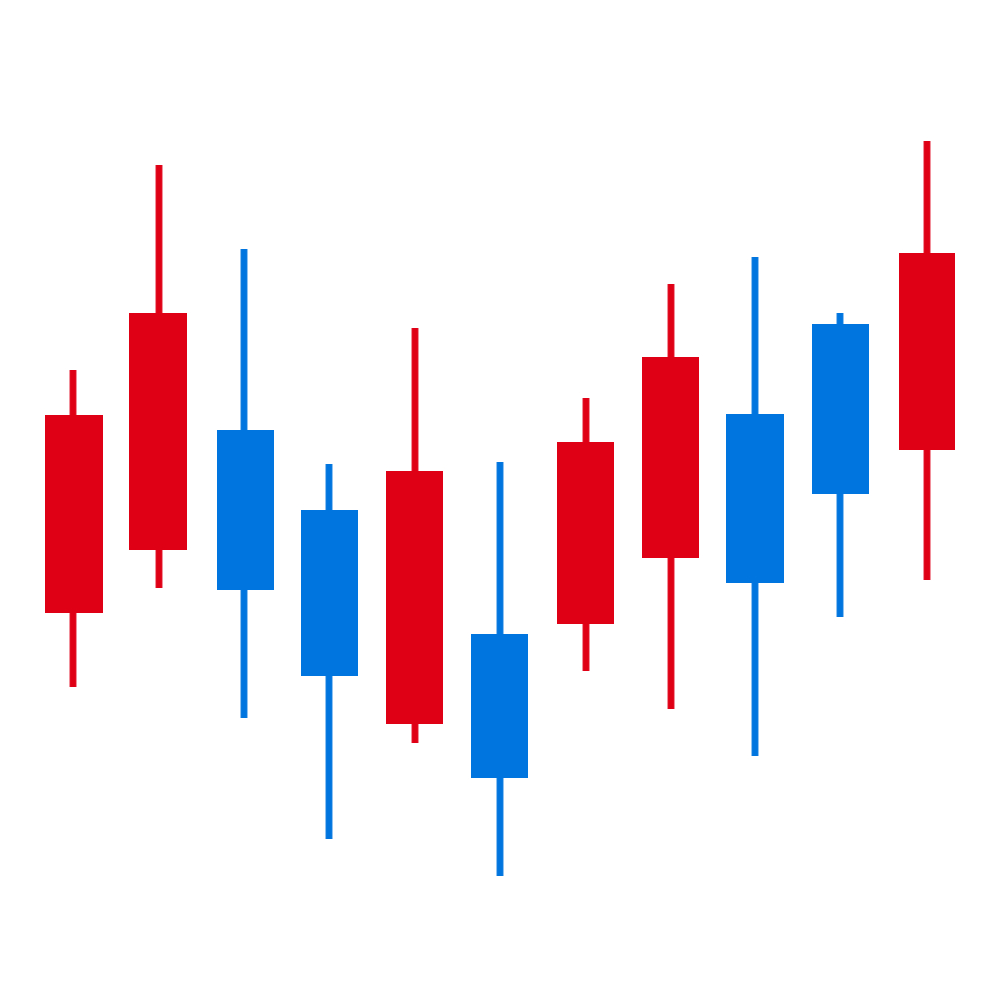ボリンジャーバンドは、相場の振れ幅(ボラティリティ)を一定期間の価格データから測定し、統計学的な観点から価格の変動範囲を予測してチャート上に表示するテクニカル指標です。
エンベロープとは、移動平均乖離率バンドとも言い、移動平均線に対して、一定のパーセンテージや一定の値幅毎に乖離線を引いたラインのことです。
この記事では改めてFX取引において重要なテクニカル分析の「ボリンジャーバンド」「エンベロープ」の基本情報と活用方法を紹介していきます。
【FX】ボリンジャーバンドとは?

引用:auじぶん銀行
ボリンジャーバンドは、ボラティリティ(価格の変化幅)を一定期間の価格データから測定し、統計学的な観点から価格の変動範囲を予測してチャート上に表示するテクニカル指標のことです。
移動平均とその算出に利用した期間データの標準偏差を計算し、移動平均に対して標準偏差のX倍を上下に加減したラインのことで、平均からどれくらい値動きにバラつきがあるかを標準偏差で算出し、値動きの収まりやすいレンジが一目でわかりやすいように表示されています。
ボリンジャーバンドがチャート上に描くボラティリティ(価格の変化幅)は、過去の値動きから予想される価格の変動範囲です。
ボリンジャーバンドにおける標準偏差とは?
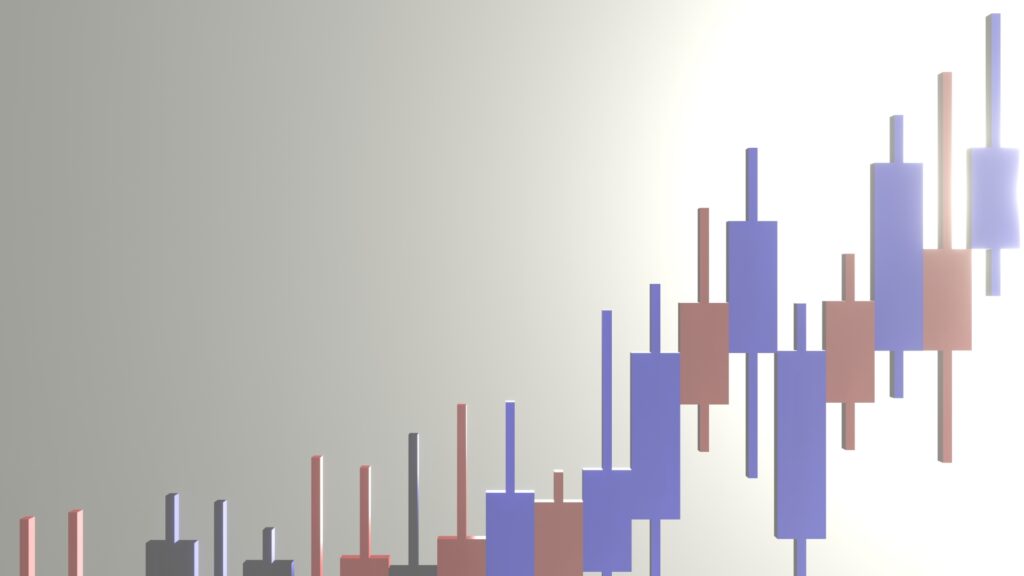
標準偏差とは、一定期間の終値など複数のデータから平均値を算出した場合に、基になった複数のデータにどの程度ばらつきを表す数値で、単位はσ(シグマ)です。
ボリンジャーバンドでも、描かれるラインを指して1σ(シグマ)などと呼ばれます。
正規分布の理論によると、この+1σ、-1σに収まる確率は約68.2%、+2σから-2σに収まる確率は約95.4%、標準偏差を3倍した3σの範囲は、基データの約99%が収まる範囲となります。
ミッドバンドの移動平均線には、一般に20~25SMA(単純移動平均線)が使われます。
ボリンジャーバンドの見方を解説

ボリンジャーバンドの利用方法には二つの方法があるので、それぞれ見ていきましょう。
1.バンドを抵抗として逆張りする
1つ目は、価格がアッパーバンド2(+2σ)と交差したときに売り、ロワーバンド2(−2σ)と交差したときに買いとする、平均値への回帰を前提とした逆張りの方法です。
価格が2σ内で変動する確率が約95%となることから、理論的に価格はそのほとんどが2σの範囲に収まるのが普通で、2σを越えるということは過去の値動きからすると異常であり、平均値を回帰すると予想するものです。
日本で解説されているボリンジャーバンドの利用法としては、この分析方法が一般的なものとされているようです。
この方法が有効な場合もありますが、開発者自身は、次に説明するボラティリティ・ブレイクアウトを使った順張りを推奨していることも知っておきましょう。
2.ボラティリティ・ブレイクアウトを使って順張り
ボラティリティ・ブレイクアウトは、収縮して幅が狭くなったバンドが横ばい状態を続けた後に価格変動を伴ってバンド幅が拡大し始め、バンド2(±2σのライン)の外で終値を付けた時に、ブレイクした方向へポジションを取るという戦略です。
ボラティリティの高まりを伴ってバンドを突破した際に、トレンドが発生する可能性が高いことを利用したものです。
ボラティリティ・ブレイクアウトの発生した相場は、その後バンドの拡大にと合わせてバンド上を沿って動く可能性が高く、これを「バンド・ウォーク」と呼び、トレンドの継続を示唆するサインと判断します。
ボリンジャーバンドは、通常ブレイクアウトした場合、ブレイクした方向とは逆のバンド(上昇トレンドでバンドの上方にブレイクした場合はロワーバンド)が先行して転換に入るため、段階的にポジションを決済する場合には、ここが最初の部分的な手仕舞いのポイントです。
トレンドと逆側のバンドの縮小への転換は、トレンドが減衰して保合いに入るとすぐに起こり、次に、ブレイクした方向のバンドが反転に転じることになりますが、相場のエネルギーが放出し切り、トレンドが終わることを意味していることから、ここがすべてのポジションを手仕舞うという方法になります。
【FX】エンベロープとは?

エンベロープとは、移動平均乖離率バンドとも言い、移動平均線に対して、一定のパーセンテージや一定の値幅毎に乖離線を引いたラインのことで、どの程度離れたかを見るために用います。
一般的には、移動平均線からある程度乖離した価格は、移動平均線へ回帰されるという考えから、エンベロープの上限・下限をトレンドの反転のポイントとして売買サインに用いたり、支持・抵抗の目安として用います。
一般的に為替市場では、乖離の目安をどの程度にするかは、25日移動平均線対比で「2~3%」と言われています。
【FX】エンベロープを用いる手法
価格が上側のラインに接近・到達した時は、反転下落の可能性が高く買われすぎと判断し「売り」のサインとなり、価格が下側のラインに接近・到達した時は、反転上昇の可能性が高く売られすぎと判断し「買い」のサインとなります。
しかし、移動平均の期間が短い場合や乖離の幅が狭いとレートが頻繁にエンベロープの両端に接近するため、設定の数値や利用上の判断には注意しましょう。
エンベロープ・ボリンジャーバンドの違い

先程もご説明した通り、エンベロープとボリンジャーバンドは一見似ていても、上下のバンドの動き方に少し違った特徴を持っているので、分かりやすく表現してみると以下のようになります。
エンベロープ
・移動平均線を中心にして、レートの乖離を%で算出
・移動平均線を中心にしていることから、移動平均線と平行してボリジャーバンドよりも
エンベロープはどちらかというと知名度の高くないテクニカル指標だったとされていますが、最近ではプロトレーダーの中でも利益を上げる為のシンプルな指標だとして注目されてきています。
ボリンジャーバンド
・値動きの標準偏差で算出
・エンベロープとは逆に、直近の値動きに強く大きくバンドの幅が広がったりする
また、エンベロープでは設定を行う際に時間軸に合わせて設定する必要があるので、現地時間との分単位設定で通常では小さな幅も時間軸設定を短くすることによっては数分内で何円もの幅が表示されてしまうケースなどもあります。時間軸設定が重要となってくるので覚えておきましょう。
またどちらの指標も、近々で起きているトレンドの上下左右する大きな動きが出ている際の安易な逆張りについては注意しなければなりません!
まとめ
ボリンジャーバンドもエンベロープも、将来の価格の動きを予測するために使われるテクニカル分析の手法です。
違いはボリンジャーバンドの各ラインは、標準偏差を使って算出され価格変動が大きくなるとバンドの幅が広がったり、変動が小さくなると幅が縮まったりと相場の変動に伴ってラインの広がりや縮まりがありますが、エンベロープは単純に、中心ラインの25日移動平均線に平行線が引かれたものとなります。